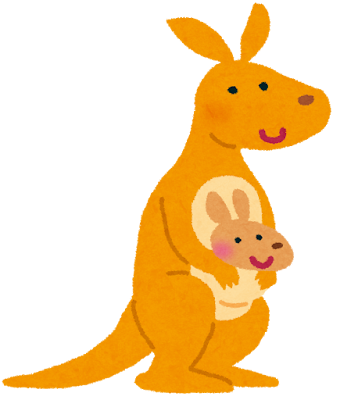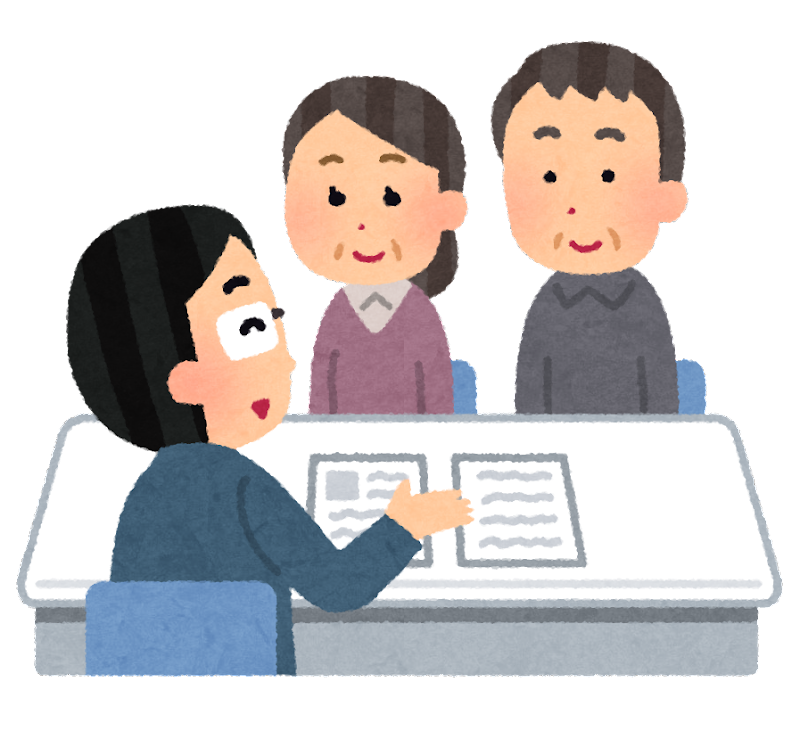いつかは・・・と思っていても、なかなか遺言書を作成しようという流れにはならない場合があると思っています。
それは、遺言書と遺書とが、本来は異なる存在なのですが、似たネーミングとなっていて、ややどちらかというと「遺言書≒遺書」という印象が出来上がっていることによるものかと想像しています。
それでは、いつ書くべきなのか・・・こればかりは、思い立った時、もしくは必要に迫られたとき(と感じた時)、ということになるのかな、というようには思います。
なんといっても、その人に遺言書を書いて!というものでもないわけですからね・・・。
とはいえ、当職が思うに、例えば推定相続人(あるいは、特定条件で推定相続人となる方)について、このようなご事情の場合は、やはり急ぎ遺言書を作成するべきであろうと考えます。
①子がいない(最初からいない、又はかつてはいた、という場合も含む。)夫婦の場合
②法定相続人の一人でも、音信が途絶えている(失踪している、など。)、あるいは交流することが極めて困難(居所不明、連絡先不明など。)である人がいる場合
③認知症と診断されている人、意思表示ができない人(何らかの障害を抱えている、昏睡状態など。)がいる場合
④日本国籍離脱者がいる場合
⑤甥姪など、日ごろから交流がないなどの状況である場合
⑥揉めそうな(そういった主張をしそうな)人がいる場合
他にもいろいろなご事情がありますが、平たく言ってしまうと、遺産分割協議の場を設定しようにも参加できない、参加しても紛糾しそう、といった場合が該当します。
もちろん参加といっても、本当にその場に来られなくても、通話やメッセージなどで意思疎通ができて協力しあえるのであれば(それから郵便による書類交換が現実に可能な地域なのであれば)、後日、その遺産分割協議を補完する方法がありますので、それにより対応可能となります。
もちろん、遺言書を作成することは必要不可欠というものではなく、もし相続開始時に存在していなければ(発見されていなければ)、遺産分割協議を行うことになるだけのこと、という言い方もあるわけですが・・・。
逆に、ほぼほぼ、どういった状況下であっても、遺言書を作成しようと思われるのであれば、ほとんどの場合、何らかの形で遺言書を作成することは可能です。
自筆証書遺言を作成する、公正証書遺言を作成する、ということも場合によっては可能ですし、他は危急時遺言などもあります。
特に公正証書遺言を作成する場合は、署名と押印(基本的には実印)することになりますが、署名ができない(手に力が入らないなど・・・この場合も公証人の判断により作成可能)、押印ができないといった場合の代替策もあります(実印に代えてマイナンバーカード提示による作成も可能)。
逆に会話ができない場合(症状により)は、自筆証書遺言、あるいは手話通訳者による遺言も選択可能な場合があります。
といったようなことから、遺言書っていつ作るのかという点については、できるだけ元気なうちに作成をした方がより良い、ということにはなりますが、よほどの状況ではない限り、何らかの方式により遺言書が作成できる場合がありますので、詳細は当事務所までご相談いただければと思います。
お問い合わせはこちら↓からお願いいたします。
ありがとうございました。